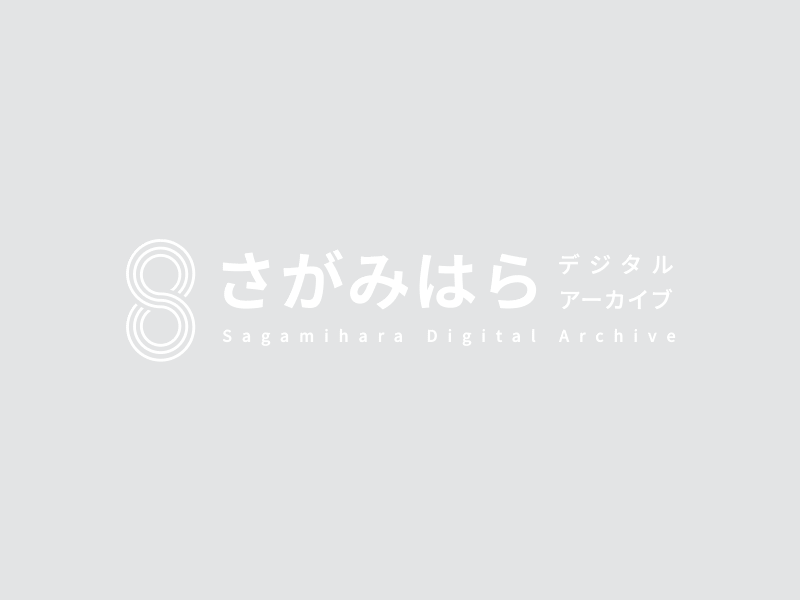相模の大凧揚げ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料名称 |
相模の大凧揚げ |
| 所蔵機関 |
文化財課 |
| 権利 |
CC0 |
| 種別 |
市指定無形民俗文化財(風俗慣習) |
| 数量 |
- |
| 指定年月日 |
平成22年04月01日 |
| 記号番号 |
指-46 |
| 保持団体 |
相模の大凧文化保存会 |
| 内容 |
相模の大凧揚げは、南区新磯地域に伝わる地域を代表する風俗慣習で、もとは5月の節句の際に男児誕生を祝って行われたものです。伝承では天保年間(1830~43年)からと伝えられていますが、凧が現在のように大型化したのが確認できるのは明治期からです。 昭和40年代までは、青年団が中心となった凧連が、昭和44(1969)年以降は、南区新磯地域の新戸、上磯部、下磯部、勝坂の4地区の自治会が中心となり、4年に一度の輪番で、凧揚げを開催していました。 平成15(2003)年には相模の大凧センターができ、保存・普及や製作技術の継承が行われています。 凧の大きさは、最も大きい新戸地区の凧が8間(14.5メートル)四方で、材料は竹と和紙です。竹で骨組みを作った後、反りを入れ、別に和紙を貼り合わせた複数の大貼りを作り、2文字の漢字を赤と青で書く、いわゆる字凧です。凧が正方形で、大貼りが脱着できる全国的にもめずらしいものです。 →毎年5月4日、5日に南区新磯地域にある相模川沿いの広場にて凧揚げが開催されています。 |
| 参考文献 |
相模原市教育委員会 1972 『さがみはら文化財 第八集 新磯の大凧』 |
| 関連URL |
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankou/bunka/1022295/bunkazai/list/1010142/1010189.html |